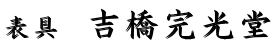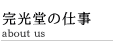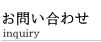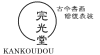??? ???? ?
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
- ?????????????? ?
- ??????????????
- ????? ????????
- ????????????????
- ?????????????
- ?????????????????
- ???????????????????
- ?????????-???
???????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????
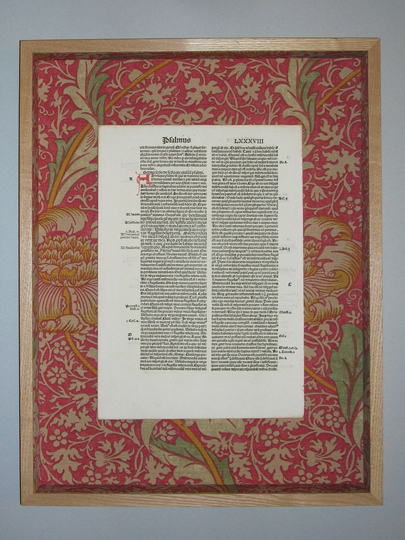
???????
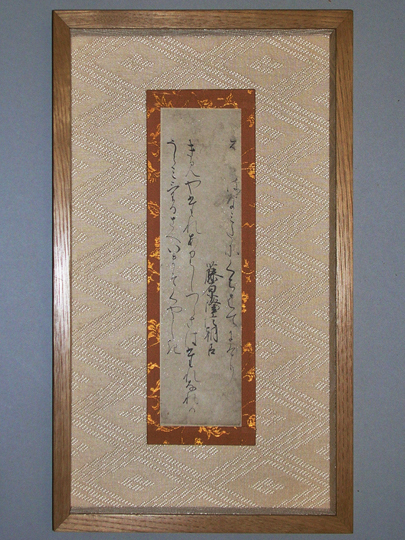
????
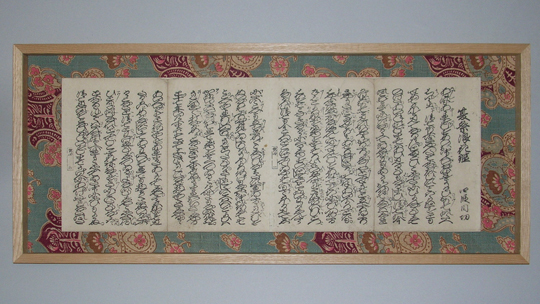
????
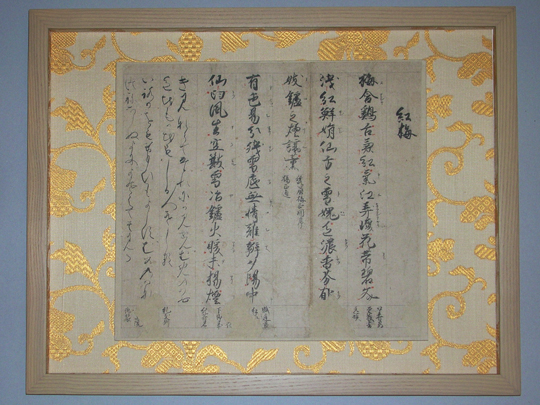
?????

???????

???????
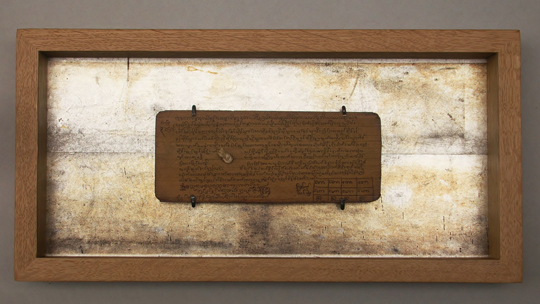
????????
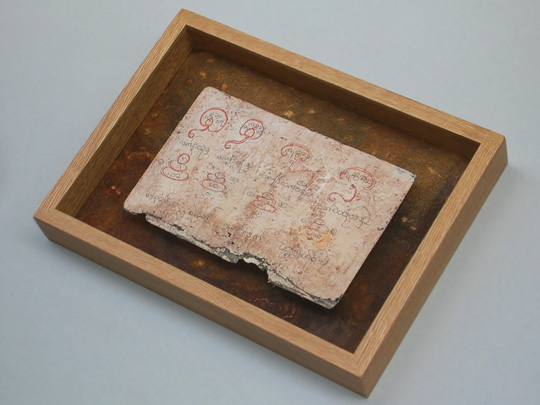
????????

????????